写研の創業者、石井茂吉が手がけた書体は、ごく一部の例外をのぞいて「石井」の二文字から始まります。なかでも、最初期につくられた石井明朝体オールドスタイルは、いまでも伝説的な人気があります。残念ながら見かける機会はほとんどなくなってしまったものの、たとえば「K-MM-A-OKL」などといった書体コード名を耳にしたことのある方も、いらっしゃるのではないでしょうか。
この石井明朝体オールドスタイルは、ウェイト(太さ)がL・M・B・Eの四種類にわかれており、時代の流れやユーザーの要望によって、少しずつウェイトが拡充されてきました。そのため、おなじ書体にもかかわらず、つくられた年代によって細部のデザインは微妙に異なっています。
とはいえ、写研の黎明期から存在してきた書体であることには変わりなく、1924年の創業からおよそ一世紀にわたって、写研とともに長いときを歩んできました。より厳密にいえば、8年ほどの試作期間をへて、1933年に生まれたのが初代の石井明朝体オールドスタイルになります。当時は印刷といえば活版の時代であり、その気になれば、活版屋さんから活字を買ってきて流用するのが一番手っ取り早かったはずです。
にもかかわらず石井が選んだのは独自開発、つまり写真植字機の特性にあわせた理想の明朝体を、自らの手でつくるという道でした。そこには活版と写植という、原理からしてまったく異なる印刷機が、書体開発の大きな壁として立ちはだかっていたのです。

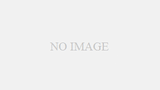
コメント